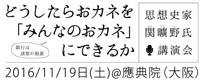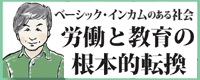今日の若い世代のもっとも切実な関心は、年金制度がまったく破綻しているという問題です。先の仁和寺の講演でも会場から「国民年金保険料を払い続けるかどうか迷っている。関さんはどう考えるか」という質問がありました。ベーシックインカムをめぐる議論はこの問題に今より深く立ち入り、若い世代のかかえる不安に応える必要があります。とにかく年金というネズミ講の破綻は明白です。しかも現状は、経済危機で苦しんでいる若い世代が今も高度成長期の恩恵に浴している高齢世代を支えるというとんでもない世代間搾取になっています。そして給与生活者の若者には源泉徴収なので保険料納付を拒否する自由もありません。
講演で私は、定年制を産業主義的な制度として廃止したうえでベーシックインカムにプラスして老年基金を設けるという案に触れました。しかしこの案の具体的な中身については論じる時間がありませんでした。そこで以下、この老年基金についての私の構想を説明しますから、皆さんがこれから年金の問題で討論する際のたたき台にしてください。
まず定年制は廃止して多くの人が生涯現役で働けるように労働環境をスローなものにすることに重点を置きます。農業関係者などは今でも生涯現役が普通なのですから、これは無理な話ではありません。しかし歳をとるとやはり体力能力が低下し病気がちになることも事実です。ですから60歳以上の人には何らかの生活保障の措置が必要でしょう。そして私の構想は、この措置を「負の所得税」方式で実施し、高齢者に政府通貨を支給するというものです。
なぜこの方式をとり、例えば高齢者には二倍のBIを支給するといったことをしないのか。その理由は、
- BIはあくまで生産と消費を均衡させるための通貨政策であり、福祉政策ではない
- BIの大幅な増額はインフレを発生させる恐れがあり、そのうえ定年制を廃止する主旨に矛盾する
- また高齢者の所得と健康状態にはかなり個人差があるということを考慮する必要がある
この方式をどのように実施するか。まず60歳以上の高齢者の基準生活費を法律で決め、BIと所得を合わせてもこの基準に達しない場合に差額を政府通貨で補填します。そしてこの基準は国や県ではなく市町村が条例で定めることにします。ただし基準は地域毎に違っても、
その理由は、
- 市町村の方が地域の高齢者の生活実態を具体的に把握できる
- 県単位で基準を設けると物価の安い地域に高齢者が大勢移住して地域の人口構成比に歪がでる恐れがある
この方式の結果、例えば横浜市と鳥取市の基準が異なったとしても、この差は地域の家賃などの物価や食費などを反映したものですから、不公平なことにはなりません。こうしてある市の基準が月20万で、そこに住む高齢者の所得がBIの8万と軽作業による月収が6万だった場合、差額の6万が市から支給されることになります。
それから最後に付け加えますが、高齢者には働かない自由、60代になったら働かないで趣味やボランティアの世界で生きるという選択も認められるべきです。これは経済ではなく文化や社会への高齢者ならではの貢献になるでしょう。ただしそういう人は自治体への所得申告がないのでBI以外の所得補助は難しいと思います
以上の私の構想をたたき台に活発な議論が始まることを期待しています。